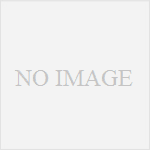「親の熟年離婚。もし将来、介護が必要になったら…」考えたくないけれど、避けては通れないこの問題。法的な責任は誰にあるのか、離婚した両親の介護を子どもだけで背負うのか、お金の問題はどうなるのか。この記事では、熟年離婚と介護にまつわる不安を解消し、親子ともに後悔しないための具体的な知識と対策を、専門家の視点も交えて分かりやすく解説します。
なぜ「熟年離婚」で「介護問題」が深刻化するのか?3つの理由
かつては「夫婦は最後まで支え合うもの」と言われてきましたが、今や日本では熟年離婚が珍しくありません。長年連れ添った夫婦が離婚すると、見落とされがちなのが**「介護問題」**です。ここでは、その背景を3つの理由から見ていきましょう。
理由1:頼れるはずの配偶者がいなくなる
熟年離婚によって、これまで当然のように支え合っていた関係が消えます。体調を崩したとき、家事や通院を助けてくれる存在がいなくなることは大きな不安です。特にどちらかが持病を抱えている場合、介護を担う人が不在になるリスクは高まります。
理由2:経済的な基盤が弱くなる
離婚後は、年金や預貯金が分かれ、それぞれの生活費・住居費を確保しなければなりません。結果として、介護にかかる費用を十分に賄えなくなるケースも。特に女性の場合、長年専業主婦だった方は、老後資金が十分でないケースが多いのが現実です。
理由3:「介護は長男の嫁が…」という時代の終焉
家族の形も大きく変化しました。核家族化が進み、「長男夫婦と同居して親をみる」という慣習は崩壊しています。離婚によって家族の関係性が複雑になると、**「誰が介護を担うのか」**が不明確になり、トラブルの火種にもなりやすいのです。
【大前提】法律上の「介護の義務」は誰にある?
介護の現場では「元夫(妻)に面倒を見てもらえないか?」という声も聞かれますが、法的な立場を理解しておくことが大切です。
離婚した元配偶者に、法的な扶養・介護義務は「ない」
民法上、扶養義務は「親族関係」に基づきます。離婚によって夫婦関係が解消されれば、元配偶者はもはや親族ではありません。そのため、介護や生活費の負担義務もなくなります。
第一次的な扶養義務は「子ども(直系血族)」にある
親の介護に関して、法的に義務を負うのは子どもです。たとえ親が離婚していても、子どもから見れば「実の親」であることに変わりありません。ただし、実際の介護内容や負担の程度は、家庭の事情に応じて柔軟に考えられます。
「扶養義務=同居して身体介護」ではない!経済的支援も含まれる
介護義務と聞くと「親と一緒に暮らして世話をする」と思われがちですが、そうではありません。経済的な支援や、介護サービス利用の手続きサポートなども立派な扶養の形です。
【子ども世代向け】親の熟年離婚。介護で後悔しないために今すべきこと
ステップ1:離婚前に親子で話し合うべきことリスト
- 介護が必要になった時のキーパーソンは誰か
- 介護費用はどの資産から捻出するのか(年金・預貯金など)
- 希望する介護の形(在宅介護/施設入居)
離婚という節目は、親の老後を考えるきっかけにもなります。お金や介護の話は切り出しにくいものですが、「今話しておくこと」が後のトラブルを防ぎます。
ステップ2:離婚後の親との関係づくり
離婚後も、定期的に親と連絡を取り、体調や生活の変化に気づける体制を整えておきましょう。また、兄弟姉妹がいる場合は、情報共有のルール作りも大切です。LINEグループや共有ノートなどを活用するのも有効です。
ステップ3:頼れる専門家とサービスを知っておく
最初に相談すべきは「地域包括支援センター」。介護に関するあらゆる相談に無料で対応してくれます。
また、「介護保険サービス」で受けられる内容を知っておくと、負担を大きく減らせます。
【当事者世代向け】「介護が原因の離婚」「離婚後の自分の介護」への備え
「介護離婚」を考えている場合
介護は精神的にも肉体的にも大きな負担です。離婚を選ぶ前に、「介護離職」だけは避けましょう。収入を絶ってしまうと、自分自身の老後も支えられなくなります。
財産分与で「将来の介護費用」も考慮できる?
財産分与の際、将来の生活や介護に必要な資金も見越しておくことが大切です。弁護士やファイナンシャルプランナーに相談すれば、具体的なシミュレーションが可能です。
離婚後の「おひとりさまの介護」に備えるには
元気なうちに「任意後見制度」や「家族信託」を活用すれば、将来の判断力低下に備えられます。
また、離婚協議書や公正証書に「もしもの時の協力内容」を記しておくことも、トラブル回避に役立ちます。
よくあるQ&A
Q. 離婚した父(母)の介護を、元配偶者に費用請求できますか?
→できません。離婚により親族関係が解消されるため、法的な請求権はありません。
Q. 親との関係が良くない場合でも、介護義務を負わなければなりませんか?
→法的には扶養義務がありますが、実際の支援方法は柔軟です。金銭的な援助や相談窓口の紹介なども選択肢に入ります。
Q. 介護費用が足りない場合、どのような公的支援がありますか?
→介護保険、生活保護、社会福祉協議会の貸付制度などがあります。早めに市区町村の福祉課に相談を。
まとめ:不安を抱え込まず、早めに相談することが未来を拓く
熟年離婚と介護の問題は、どちらも人生の大きな転換点です。だからこそ、ひとりで抱え込むと心が疲れてしまいます。
介護も、離婚も、「自分を責める」テーマではありません。
少しずつ、助けを借りながら前に進むことで、必ず道は見えてきます。
公的な窓口や専門家は、あなたの味方です。
そして何より、「親を思う気持ち」も「自分を守りたい気持ち」も、どちらも間違いではありません。
焦らず、できることから。
その一歩が、未来のあなたと家族を守る力になります。