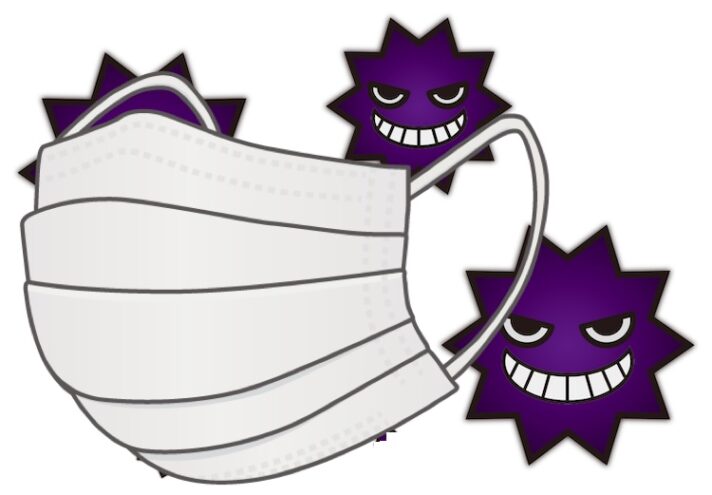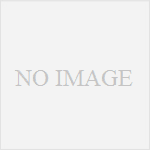コロナ禍が落ち着いた今も、街にはマスク姿の人があふれています。
それは本当に「健康」を守っていると言えるのでしょうか。
薬剤・免疫学に詳しい伊豆里悟医師は、「感染を防ぐこと」と「健康を保つこと」は別物だと語ります。
PCR検査の過剰感度、過度な消毒、そして長引くマスク生活――。
私たちはいつの間にか、“恐怖に支配された予防”に慣れすぎてはいないでしょうか。
本来の「予防」とは何かを、改めて見つめ直す時が来ています。
今回は、医師が語る“マスク社会の本当の姿”と、“健康を守るための新しい視点”を紹介します。
「感染を防ぐこと」と「健康を守ること」は、同じではない
コロナ禍から数年が経った今でも、マスクを外せない人が多い日本。
街中では季節を問わずマスク姿が目立ちます。
一方で、海外ではすでにマスクを外す生活が一般的になりつつあります。
そんな中、「医学的に見て、マスクや過剰な消毒には限界がある」と語るのは、薬剤・免疫分野に詳しい医師。
同氏は、「感染症対策の目的がすり替わっているのではないか」と疑問を呈します。
PCR検査の“過剰感度”と「恐怖の連鎖」
医師によると、日本で行われていたPCR検査の一部は、世界基準よりも高い増幅回数(CT値)で実施されていた時期があり、その結果、実際には感染していない人まで「陽性」とされた可能性もあったといいます。
「40回も増幅すれば、微量のウイルス片でも検出されてしまう。結果、必要以上に“感染者”が増え、社会全体が恐怖に包まれたのです」
“ウイルスが怖い”という気持ちは当然ですが、恐怖に支配された社会では、冷静な判断が難しくなります。
医師は、「本来の予防とは、ウイルスを探すことではなく、免疫力を高めること」と語ります。
アルコール消毒やマスクが「逆効果」になることも
多くの人が信じてきた「手指のアルコール消毒」や「常時マスク」。
しかし医師は、それらが防御のしすぎによる弊害を生んでいると指摘します。
「皮膚にはもともと防御のための常在菌がいます。
過度な消毒でそれを取り除いてしまうと、逆にウイルスの侵入を助けてしまうこともあるんです」
また、マスクについても次のように語ります。
「マスクの内側は呼気で湿度が高く、ウイルスや雑菌が繁殖しやすい環境。
一日中同じマスクを使うことで、かえって感染リスクが上がる可能性があります」
「マスク社会」が子どもたちに残したもの
医師が特に懸念しているのが、長期間マスクをつけて過ごした子どもたちへの影響です。
「顔の表情を隠したまま育った“コロナ世代”の子どもたちは、自己表現や人との関わり方に影響を受けている可能性があります。
“黙食”“前を向いて話さない”といった生活が長く続いたことが、心の発達に影を落としていないか――注意深く見守る必要があります」
マスクは確かに「安心感」を与えてくれました。
しかし、同時に「声を上げづらい社会」を生み出してしまったのかもしれません。
「恐怖」ではなく「理解」で健康を守る時代へ
「人間の体は本来、環境と共に生きるようにできています。
ウイルスを“敵”として排除するよりも、共存できるよう免疫を整えることが、真の予防につながる」
医師の言葉には、現代社会に必要な“視点の転換”が込められています。
マスクを外す・外さないの議論よりも大切なのは、自分の健康を自分で見つめ直すこと。
正しい知識と冷静な判断をもって、「不安」よりも「理解」で生きる社会へ――。
息苦しい日々が続いても、深呼吸をすれば世界は変わります。
マスクの向こうにある笑顔を、少しずつ取り戻していきましょう。